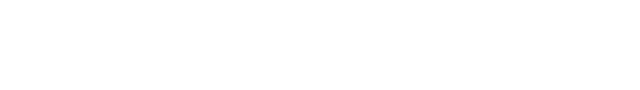院長ブログ
歯みがき①
(2022.04.21更新)
[歯みがきの基本]
・1ヶ所20回以上、歯並びに合わせて歯を磨きましょう。
・歯ブラシの毛先が広がらない程度の軽い力で磨きます。
・歯ブラシの毛先を歯と歯茎の境目、歯と歯と間にし… ▼続きを読む
インプラント⑨
(2022.04.14更新)
インプラントとは、歯を失ったぶいのあごの骨に人口の歯根を植え込む手術を行って歯をつくることにより、かみ合わせと見た目を回復させる治療です。
現在使用されているインプラントのほとんどは… ▼続きを読む
むし歯②
(2022.04.01更新)
歯科材料のポーセレンやコンポジットレジンは天然歯と外観が似ているため、前歯にも用いられることがよくあります。
奥歯は咬合圧が強い等の理由により、インレーやアマルガムが… ▼続きを読む
むし歯①
(2022.03.11更新)
むし歯の原因のひとつに糖質があります。
糖質には砂糖やデンプンなど様々な種類があります。
酸生産能は糖質の種類によって異なり、砂糖の主成分であるスク… ▼続きを読む
矯正②
(2022.02.18更新)
矯正を行う時の問題点として、う蝕(虫歯)、歯肉炎、歯根膜炎、歯の痛み、装置の破損、歯根吸収、口内炎、発音障害、咀嚼障害、不眠、体重減少、聴覚過敏、耳鳴り、ささくれ、金属アレルギーなどがあります。… ▼続きを読む
矯正①
(2022.01.30更新)
矯正を行う時期については、個々の症例で大きな差があります。
一概には言えませんが、子供で1〜5年程度、1〜3年近く治療が必要です。
子供の場合、成長… ▼続きを読む
おやしらず③
(2022.01.20更新)
親知らずを抜いた後は頬が腫れたり、発熱することがあります。
また、下の親知らずを抜く際に下歯槽神経を傷付けて唇や顎にしびれが出ることがまれにありますが、通常は1ヶ月か… ▼続きを読む
おやしらず②
(2022.01.07更新)
太古の昔、ヒトもかつては親知らずが正常に生えていました。
大昔のヒトの食生活は、「煮る」「焼く」などの調理技術が乏しく、木の実や生肉など硬いものをかじって食べる習慣が一般的でし… ▼続きを読む
おやしらず
(2021.12.11更新)
乳歯の生え始めとは違い、親がこの歯の生え始めを知らないため親知らずという名がつきました。
「辞典」には「親不知歯」として記載されえおり、「20〜25歳ごろに生えるので… ▼続きを読む
「インプラント⑧」
(2021.11.09更新)
現在のデンタルインプラントの10年生存率はシステムや、患者様の年齢などにより左右されますが、約90%です。
また、インプラント治療を受ける患者様の平均年齢は40〜50才代一番のボリューム… ▼続きを読む